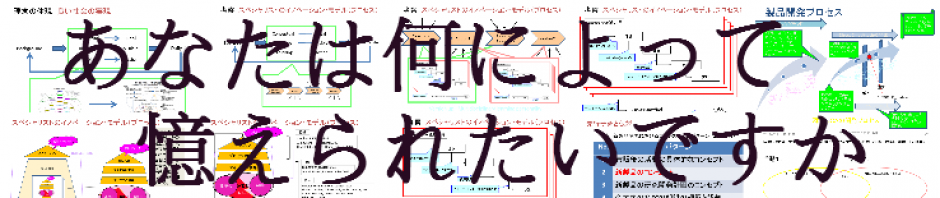社会はマインドの写像
2019/02/02
「集めたモノを自然と分類できるようになり、新しいカテゴリーを見つけると友達に自慢してました。やがて、音楽において新しい才能を発掘して、友達に教えてあげる喜びに辿り着きました。集めたモノを分類する感覚は、Footballやバスケットボールでのプレイの型や、製薬会社の仕事の定型化や、社会アーキテクチャを構成する要素の抽出に役立っています。新しい才能を見つける感覚は、良いFootballer、Coach、映画監督、そして自分に成長を齎してくれるヒトを見つける嗅覚へと成長しました。」
(シモムラタクジ, マインド・ドリブン・ソサイエティ α, affirmativeArchitect出版, 2018)
今回の話題に入る前に、マインド・ドリブン・ソサイエティの名前の由来について少し触れさせて下さい。
すべてのヒトが幸せになれる地球、その社会をこう名付けました。
マインドとはヒトの「今」そのものを指します。
過去も未来も「今」に畳み込まれています。この「今」の中心には、そのヒトの幸せあります。その幸せはそのヒトにとって大切にしている何かと繋がっています。この幸せを叶える行動をヒトは取っていると私は考えました。
この幸せは状況によって変わりますが、大切にしている何かは状況によって変わりません。ヒトの人生を考えるとこの「大切にしている何か」が行動する力になっている。志を大切にしているヒトは志ドリブン、思いやりを大切にしているヒトは思いやりドリブン、理念を大切にしているヒトは理念ドリブン、おもてなしを大切にしているヒトはおもてなしドリブン。
一人一人、大切にしている何かを表現すると多種多様になるでしょう。しかし、その表現したモノの自分の中の位置付けは、みんな同じになると私は考えています。それを「マインド」としました。
自分の大切にしている何かを行動に変換するのがマインドの役割です。
すべてのヒトが自分の大切にしている何かを行動に変換できる社会、そんな社会はすべてのヒトが幸せになれる。この想いを込めて、マインド・ドリブン・ソサイエティと名付けました。
あなたがマインドにすべてのヒトが幸せになれる社会を描かれていれば、あなたが行動し続けることによりそれは実現します。
社会はマインドの写像です。
それでは、本日の話題に移ります。
2018年9月18日、環境ビジネスの社長さんとお互いのビジネスの未来について語り合いました。
この社長さんは拙著「マインド・ドリブン・ソサイエティα」を購読されていました。
以前取り上げた、世界青少年「志」プレゼンテーション大会で、プレゼンターの12名のうち4、5名が「居場所」をキーワードにしていたことから日本の社会の現状が話題に。
例えば、子供への親の虐待は、親が社会の中で辛い思いをしていることが原因かも知れません。
親が会社員の場合、その会社の仕組みがそのまま親の社会環境になります。
働き方改革はマネジメント改革。
生産効率を高めることが重要課題とされています。少ないヒトでも同じ生産ができる体制です。
また、会社が資本家からお金を借り入れているのであれば、その返済のために利益を上げて行かなければなりません。
これも生産性の課題です。原材料の変更や標準化により原価を抑えられるかどうか、仕事の単価をあげられるかどうか、商品やサービスの販売先や販売数を増やせるかどうか。これらが利益を上げて行くポイントになります。
拙著において働き方改革で提案しているのは、「3人プロジェクト」と「社員のコンサル化」です。
具体的な方法や体制の移行については、拙著をご参照下さい。
社員の能力開発と、社内体制にプロジェクトを組み込むことで働き方改革を実現します。
いずれも、社員のやりがいが前提になります。
やりがいを持った社員がお互いに信頼関係を構築して新しい何かに挑戦する文化へと徐々に変わって行きます。
一人一人が自らの「居場所」を社内外に作る働き方を提案しています。
次に、大きな社会体制の話題になりました。「生きるために働く」状況が続く場合、一人一人が個人事業主となり、会社でも働けるし、個人でも働ける社会体制が好ましいと考えました。
関係性が固定されると、ハラスメントが起きやすいからです。
お互いの関係性が悪くなって関係性の修復が難しい場合、会社で別々の仕事に変わって新しい仕事に邁進することも可能ですし、会社を辞めて個人で仕事をすると良い関係性の仲間と一緒に仕事をすることも可能になります。
選択肢が増えて、自分の仕事の可能性が広がります。
もちろん、私のコンサルでは、お互いの関係性を良好にするポイントから入ります。
サッカー型組織は、ポジションは役割であり、個人間の能力の優劣を示すものではないことを前提としています。
個人がキャリアの設計図を持ち、仕事の選択は、そのキャリア計画を実現するため。
こんな組織や社会が最も生産性が高くなるというのが私の仮説です。
意図した行動を振り返る。これをやり続けた先になりたい自分が現れる。
“それを端的に述べるのであれば、1)学習や変化の源泉を「経験」においている点、そして、2)変化につながるきっかけとして「振り返り」を位置付けている点です。”
(中原淳, 中村和彦, 組織開発の探求, P.81, ダイヤモンド社, 2018)
「生きるために働く」状況をなくすには、ベーシックインカムと食糧とエネルギーの無料化が必要になるでしょう。
エネルギーを無料化すると、結果的に食糧も無料化し、モノの生産(機械を動かす部分)が無料になります。
この組み合わせで生きるために働く必要がなくなれば、原材料も無料にできます。枯渇すると困る原材料は調整が必要ですが。
こうなるとすべてのヒトが生きることを楽しむ社会になります。
そのためには、エネルギーの無料化が大きなポイントになります。その実現には人工知能(AI)が大きな役割を担いそうです。
最後は、汎用人工知能(AGI)の話題になりました。
AGIとはヒトのように考えることのできるAIです。
まだ、実現していません。
チェスが強い、囲碁が強い、将棋が強い、このように使用目的を特化した特化型AIは幾つか実現しています。
AGIはそれだけで、チェスや囲碁ができるし家事もできるし仕事もできます。
AGIの開発の課題について情報交換しました。
まず、脳が体からの情報をinputして、体に情報をoutputする身体性の課題です。
その一部を解決する手段として、コンピューター上に身体を持ったアバターを作り、AIを使ってそのアバターを動かす事例を紹介して頂きました。
例えば、野球選手のアバターを作り、コンピュータ内でプレイをさせて、野球選手としての動き方を学習したら、そのプログラムをロボットにインストールする。工場での生産現場にも技術伝承の仕組みとして応用できそうですね。
次に対話です。
一人一人が蓄積してきた膨大な知識、それも直ぐに取り出せるように頭の中で整理されている知識をAIに実装することが課題です。これができないとヒトと同じように即座の会話のやり取りができません。この課題の解決には「概念」や「意識」、「幸せ」への更なる理解が必要になります。
最後に私が開発しているヒトの認知の壁を突破するAIです。
社長さんには非常に興味を持って頂けました。認知の壁を突破する人工知能が社会基盤になると、あらゆる認知の壁を突破して悟ったヒトが沢山現れる未来がやってくるかも知れません。悩みを解決しながら、幸せに向かって行動を続けるヒトの溢れる未来になるでしょう。
「人工知能と社会 2025年の未来予測」(AIX監修, 2018, オーム社)には、AGIや、ヒトのように成長するロボットの現状がまとめられています。AGIが解決する課題を設定して、完成品のinputとoutputを決めて、現状の技術と新たな技術を組み合わせて、ヒトが認知の壁を突破するのを支援する人工知能を開発しますね。
AIそのものが課題を設定し、必要な情報をinputし、その課題を解決するための世界観を構築し、段階的に課題を解決する。人工知能がinputした情報を分解して分類して構造化して知識体系として記憶します。その行動はヒトと同じように、あたりをつけて詳細を明らかにする。それが、ヒトの幸せに繋がる。人工知能そのものの開発だけでなく、ヒトの能力開発(この過程は認知の壁の突破の連続になります)に役立つ人工知能を社会基盤とした新しい社会アーキテクチャ(構造)を提案し、多くの関係者とそれを実現して行きます。
あなたも一緒に取り組みませんか?
あなたの意思決定が世界を創る。
#汎用人工知能
関連記事
-

-
自己効力感の源 アルバート・バンデューラさん
Check社会はマインドの写像皆さん、こんにちは。理念の体現.com のSHIM …
-

-
ご相談:2023年に観光協会と一緒に取り組みたい事業(下村)
Check社会はマインドの写像三原観光協会 専務理事 中重隆俊様 先ほどは、お電 …
-
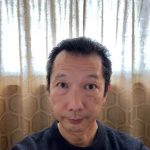
-
【お礼】principleからマインド・ドリブン・ソサイエティへの相転移(2019/06/29)高評価148 ありがとうございます
Check社会はマインドの写像2024年11月22日 ブログ「理念の体現」をご覧 …
-

-
コーチング 会話の間を取る
Check社会はマインドの写像あなたの意思決定が世界を創る。 意思決定コンサルタ …
-

-
違いからくる美しさ
Check社会はマインドの写像「自分から表現しなければ、あなたの世界は広がって行 …
-

-
#Qatar2022 #SamuraiBlue の皆様へ 溢れんばかりの期待を届ける
Check社会はマインドの写像#SamuraiBlue の皆様へ、 私は日本サッ …
-

-
【お礼】投稿「物語 VoucherMoney お金の最終到達点」(2021/10/31)高評価500 ありがとうございます
Check社会はマインドの写像2025年8月15日 ブログ「理念の体現」をご覧に …
-

-
生命体のプリンシプル
Check社会はマインドの写像「産業革命以降、綿々と築いてきた規模の経済には、元 …
-

-
的確な考え方のフレーム設定-的確なフレームづくりのための基本コンセプト 籠屋邦夫さん
Check社会はマインドの写像理念を磨け、新たな価値の連鎖を生み出せ、意思決定ス …
-

-
GDP至上主義への疑問
Check社会はマインドの写像2020年2月13日起案、16日脱稿 昨日から # …
- PREV
- プレゼンの前のフラフラな体験
- NEXT
- チャレンジと知識技術の習得