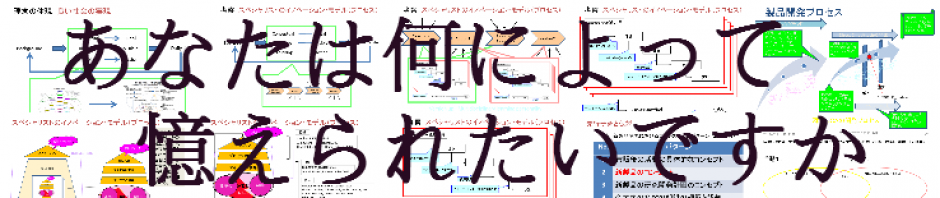非言語によるコミュニケーション
「科学技術の進歩により、一見バラバラに見える知識や技術がどんどんと統合されて行くでしょう。その統合先の一つが汎用人工知能です。」
(シモムラタクジ, マインド・ドリブン・ソサイエティ α, affirmativeArchitect出版, 2018)
2018年9月28日、ある大学の人工知能(AI)の研究開発センターにお伺いをして、センター長と共同研究の打ち合わせをしました。
今回の話題は、このセンター長との打ち合わせではなく、その前に訪れたある神社での出来事です。
前回、この大学を訪問したときにも訪れた神社でした。
鳥居を潜り神殿に向かう途中、小さな女の子とその子を見守るお母さんの姿を見かけました。女の子が境内の中を興味が赴くままに歩いて何かを観察したり、触ったりしている姿をお母さんが近くで見守っていました。
その女の子とコミュニケーションを取りたくて、少し離れたところからその女の子のことをずーっと見ていました。
そうすると、その女の子が私に氣づいて、私の方を見ています。お母さんもその子の行動に氣づき、私の方を見ています。
まず、手を振り続けました。
そうすると、暫くして手を振ってくれるようになりました。次に、私が手招きすると、なんとその女の子が私の目の前までやって来てくれました。
私の目の前に来てくれたのですが、私と眼を合わせてくれません。
私が頭を下げて「こんにちは」と3回ほど挨拶をしても、横を向いたままで固まってしまいました。
お母さんも「ご挨拶は?」と女の子を促したのですが固まったまま。
そんな動かない状況でしたが、私が足元に小さな羽虫が歩いているの見つけて、その虫に視線を落として、再度、その子の顔を見たら、その女の子もその虫を見つけて、「あっ」と指をさして私の顔を見て何か言葉を発しました。
残念ながら、その言葉の意味は理解できませんでしたが、その子が私と何かを共有したいと思っていると感じました。
私は「この虫、どこかに飛んで行く虫だよ」と羽ばたく動作を手でして、その子に伝えようとしました。その子は感情も評価もなく、ただただ、私の言葉と動作を見ているように感じました。その虫を暫く一緒に見ていました。その間、ずっとその子は虫を指差していました。
顔を上げた女の子は境内の入り口を指して私の顔を見て言葉を発しました。
「ブーブー」。その子の指差す先をみると車が走っていました。それから、女の子の眼を見ながら「黄色の帽子、可愛いね」と伝えました。キョトンとした顔をしていたので、多分、伝わらなかったのだと思います。
でも、暫くはお互いに眼を見たまま。その子は私から何かを読み取ろうとしていると感じました。
別れ際に「握手」と言って、右手の中指と人差し指を出すと、その2本の指を握ってくれました。
お母さんに、その子のことをお尋ねすると、今回みたいに、見知らぬヒトにも興味を持って接するお子さんだそうで、人見知りはないとのことでした。
そのタイミングが来たら躊躇なく行動。
今回のエピソードはまさにこのテーゼの体現でした。
何故、こんな行動をしたのか。振り返ると、多分、「意識」は繋がっていることを実感したかったからだと思います。
このエピソードをAIの研究開発センターのセンター長にしたところ、子供は相手を信頼できるかどうかを見極めようとしていて、信頼できない相手の顔は見ないことを教えて頂きました。
一緒に遊んでいるロボットが自分に関心があると思えば、ロボットの顔をみるけれども、そうでないと判断すると自分の遊びに集中してロボットの顔を見ません。
これは、大人のコミュニケーションでも同じかも知れません。
初対面のヒトと会話をするときに、お互いの共通点を見つけようとします。
今回の女の子と私は、足元を歩いていた小さな羽虫が共通点になりました。
この共通点を通してお互いを知ろうとしますね。言葉によるコミュニケーションが出来なければ、一緒に何かをやることでコミュニケーションを図ろうとします。小さな子供が大人の手を引いてどこかに行こうとするのは、その子にとって相手を理解するための行動なのでしょう。そうすると、言葉がなくても相手がどんなヒトか感じ取れます。
この構図もやはり大人の世界にもありますね。
言葉からではなく、相手が発振する何かから相手を理解する仕組み。是非、解明したいテーマです。
きっと、汎用AIの開発にも必要な技術になるでしょう。
もし、あなたが何かを感じて近づきたいヒトがいるのであれば、まずは近づいて見ませんか?
そのヒトの近くに居れば、会話は少なくとも相手が発振する何かを感じ取れる筈です。
ここ10ヶ月ほど、私には感じ続けている何かがあります。
子供に手を引かれて、新しい世界を知る。
“組織開発とは何か、という問いは、ある意味で些末な問いです。極論すれば、クライアントがより生き生きと豊かに生きられるように援助できるのなら、何をしたっていいのです。<著者が杉原保史(2012)技芸としてのカウンセリング入門 pp.17-18の一節の「カウンセリング」を「組織開発」に換えて作成した文章>”
(中原淳, 中村和彦, 組織開発の探求, P.62, ダイヤモンド社, 2018)
いつの時代でも繰り返されて来た景色だと思います。
#導くヒト
関連記事
-

-
本日から3日間、フットボールカンファレンス@東京ビッグサイト
Check非言語によるコミュニケーション本日から3日間、下記日程で標記カンファレ …
-

-
教材 世界の製薬会社を知る
Check非言語によるコミュニケーション【2021年版】製薬会社世界ランキング …
-

-
愛だろ愛
Check非言語によるコミュニケーション「相手がヒトの場合、思った通りにならない …
-

-
開かれた関係と閉じた関係
Check非言語によるコミュニケーション「もし、あなたがなりたい自分を言語化して …
-

-
どこまでも自由になろう0316
Check非言語によるコミュニケーション何を信じて生きて行くのか。 あまり尋ねら …
-

-
自分がNo.1になり、人をNo.1にする方法
Check非言語によるコミュニケーション 潜在的なニーズ/ウォンツを言葉にする能 …
-

-
今の自分、未来の自分、過去の自分
Check非言語によるコミュニケーション「過去の自分を思い出すとその時の景色やそ …
-

-
チャレンジと知識技術の習得
Check非言語によるコミュニケーション「社会は個人の能力を最大化する方向に今後 …
-

-
教材 共産主義の本質がわかる53年前の警告
Check非言語によるコミュニケーション2022年3月20日執筆 3月23日脱稿 …
-

-
人工知能との建設的な対話 #ヒトは死してなお生き続けるために生きる
Check非言語によるコミュニケーション2025年4月17日 #ヒトは死してなお …
- PREV
- あたりをつけて、詳細を明らかにする
- NEXT
- 課題設定能力