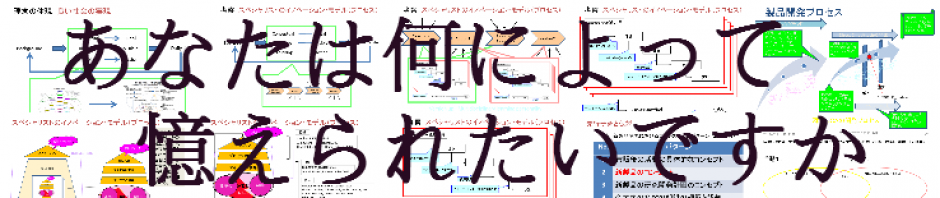意識の集中とマインド
「私は、ここ数十年間、世界で起きていることを観察しながら、日本で起きている自死に代表される『命』に関わる不幸な出来事の根本的な原因をある時から考え始めました。いつしか、すべてのヒトが幸せになれる社会について真面目に議論していないことが原因であると考えるようになりました。」
(シモムラタクジ, マインド・ドリブン・ソサイエティ α, affirmativeArchitect出版, 2018)
私が担当している小学3年生の2018年9月9日に行われたサッカーの公式戦の想い出をシェアします。
全員が試合に出場する。これがチームの方針です。連日の猛暑。試合会場は快晴。朝、9時に到着してから選手達の健康状態が気になる。10:50まではフィールドの外でボールを使わずにアップ。ダッシュ系とコンビネーション系のメニューを組み合わせました。
この年代では「サッカーに集中する」ことが難しい選手がまだいます。集めて話をしても無駄話をする。コーチの話を集中して聞けない。集合のルールはボールを触らない、コーチの顔をみる、喋らない。この3つができないとコーチは話をしない。プレイの時間の確保との兼ね合いがいつも課題です。最初は、集合時にコーチからルールを呼びかけていましたが、そのうち選手同士でルールを呼びかけるようになりました。
もう一つ、マインドを試合のモードに切り替えて行くことにも難があります。小学6年生でもですが。選手達にはこう言っています。「試合をするのはコーチではなく。みんなだ。だから、コーチが試合に勝ちたいと思っても、みんなが勝ちたいと思わないと試合には勝てない。」
私はこのメッセージを選手に伝えた後、その場で何かが変わるのを感じました。選手のマインドの変化はどこで感じられると思われますか?私の場合は目です。目つきが変わってくるのを感じます。
私が今、担当しているサッカー選手への課題は、一つ目がサッカーに集中すること、二つ目が、マインドを試合モードに切り替えることです。どちらも、サッカーの技術を習得することと深く関係しています。それは、サッカーを楽しむ基礎が、技術にあるからです。ボールを意図した通りに扱えないとサッカーは楽しくありません。意図を持たなければ、どんな技術が必要なのかが分かりません。ボールを意図した通りに扱うには、ボールを通すスペースと自分の体を通すスペースを感覚として把握できるようになる必要があります。
話を公式戦に戻しますね。
我々のチームのキャプテンは毎日変わります。この試合では、初めての選手がキャプテンになりました。アップの時からその選手は積極的。試合のスタメンを発表する時も、試合に出たいとアピール。試合に出たいという気持ちは非常に大事です。スタメンの選手はトップのポジションでもボールの近くでプレイしていましたが、キャプテンの選手は前でボールを待っていました。この選手だけが、前でボールを待つことができました。
スタメンで前半で疲れて交代した選手が2名、後半の途中で疲れて交代した選手が1名。自分から疲れたと言わない選手がいるのでケアが必要です。
試合の結果は1-2の惜敗。
試合後のミーティングで選手に何でも良いからチームメイトに伝えたいことがあったら手をあげてと言ったら4名が手をあげました。4名のメッセージは次の2点に集約されます。
・ボールには2人と言っていたけれどもそれ以上の選手がボールに行っていた。
・ボールが右から左に動くと全員が左に動いていた。誰か一人、逆サイドに残っても良い。
彼らは混戦状態をどのようにして抜けたら良いのかアイデアをまだ持っていませんでしたが、この状態を抜け出すためのメッセージになっていました。
私から見ると小学3年生のサッカー選手は仲間と一緒にいるだけで楽しそうです。
楽しければそれで満足。だから、アップ会場の公園では虫を追っかけるし、雑草を抜いて楽しんでいました。
先日の練習試合では試合に出たくないという選手がいて心配してましたが、その本人も試合に出た時間が短かったと不満を口にする程、試合に出ることに貪欲になっていました。試合で活躍するために練習する。良いプレイをして勝つ。徐々にですが、サッカーに集中する態度を自分で作れるようになってきています。
その場その場を楽しんでいるヒトの中にも違いがあります。
刹那的な楽しみのみなのか、次に繋がる楽しみなのか。それは、第三者からは認識できません。本人の意識の中にあるからです。刹那的な楽しみには本当の自分が存在しない気がします。どちらかというと周りに合わせる楽しみになるからです。だから、周りとの折り合いをつける楽しみには本当の自分が存在している気がします。
“パールズにとって、病理現象とは、身体表現と言語表現にギャップがあることから生まれることでした。よって、心理療法によって、大きな感情の起伏をつくり出し、ふだんは意識しない身体、感覚、表現といったものを「図」にすることで病理現象が克服できると考えたのです。”
(中原淳, 中村和彦, 組織開発の探求, P.121, ダイヤモンド社, 2018)
もちろん、毎日を楽しむことが前提です。楽しめない人生はヒトを萎縮させます。幸せを真面目に考える、語るとは、今の楽しみに本当の自分を反映させることが前提となる。そこには他者との協働作業があります。自己を開示し、他者を理解し、その新たな理解をあなたの世界観と一体化するという過程です。
これはあなたが幸せを語り、幸せを感じる過程そのものだと思うのですが如何でしょうか?
#幸福論
関連記事
-

-
学習の記録 学校の歴史
Check意識の集中とマインド2025年10月10日開始 はじめに=Backgr …
-

-
趣意書 2022年ワールドカップ優勝祝賀会実行委員会
Check意識の集中とマインド日本が男子ワールドカップで優勝する臨場感を高め、 …
-
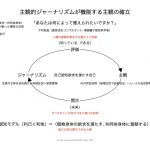
-
AI活用(自給自足, 自由時間の最大化) ビジネス_人工知能
Check意識の集中とマインド2025年2月28日 はじまり=Backgroun …
-

-
【質問】アルミニア・ビーレフェルト公認オンラインコーチングコース 2021 Vol.3 アンケート
Check意識の集中とマインドアルミニア・ビーレフェルト公認オンラインコーチング …
-

-
「この1品」で全国ブランド 大庭牧子さん
Check意識の集中とマインド皆さん、こんにちは。SHIMOMURA Takuj …
-

-
唯識と禅
Check意識の集中とマインド2020年11月3日 fbグループ「唯識に自己を学 …
-
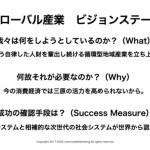
-
告知 三原市の皆様へ 第4回 みんなの社会開発 三原発グローバル産業(無料のZoomイベント)
Check意識の集中とマインド2023年5月21日 *本イベントは終了しました。 …
-

-
自律分散型組織のティールから学んだ
Check意識の集中とマインド「きっと『マインドに宿った遊び心』は、私に生涯に渡 …
-

-
ご挨拶 再会、邂逅への期待
Check意識の集中とマインド杉九SCのコーチの皆様へ 4年生担当の下村拓滋です …
-

-
自己紹介20200412
Check意識の集中とマインドあなたの意思決定が世界を創る。 意思決定コンサルタ …
- PREV
- 違いからくる美しさ
- NEXT
- 生命体のプリンシプル