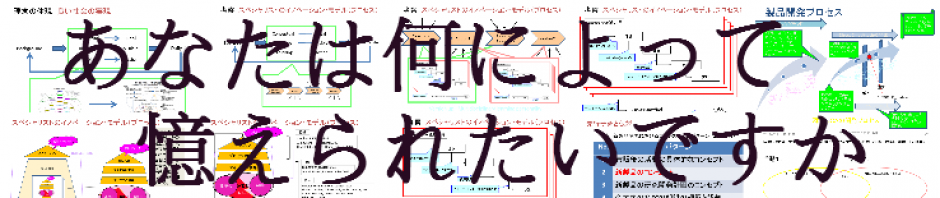学習の記録 学校の歴史
2025/11/22
2025年10月10日開始
はじめに=Background
来年、2026年9月に第36回日本教師教育学会が広島大学で開催される。
私は「地域自給自治社会におけるコミュニティスクールの役割」をテーマに自由研究発表とラウンドテーブルを開催する。
このテーマを選んだのは、欧米主導の戦争文化に強い影響を受けて来た人類史が転換期を迎えているから。この転換期をソフトランディングで乗り切る手段が地域自給自治社会であると私が確信しているから。地域自給自治社会が戦争文化を平和文化へと回帰させる。それは、生産の主体が会社員から地域住民へ回帰する未来になる。戦争文化を支えているのは債務貨幣制度と企業社会主義。通貨発行権者が通貨を発行しする時には利子がある。発行した通貨を受け取った者は受け取った通貨以上の通貨を将来かき集めなければ借金を返済できない。人類史の中で最初に借金したヒトは、2番目に借金をするヒトが現れない限り借金を完済できない(詳しい説明はこちら)。
たった一つの行動原理、principle、が我々の世界を創っている。そして、我々はprincipleを動かし、に動かされている。
1973年からすべてのヒトが幸せであり続ける地球をOutcomeとし、そのenabler(それを可能にするモノ)をprincipleと仮決めして、principleおよび到達点への道筋を探求してきた。
探求の枠組みを(認知の法則=宇宙の法則, 認知=宇宙)として、あらゆる認知モデルを完全混合した結果、principleの定義(自己認知欲求を満たす自己, 自己=principle)を明らかにした。
我々は自己認知欲求を満たす主体であり、同じ認知の枠組みを持っているが、身体(個物身体, 共同体身体)が異なるため、共同体体験速古物記憶の実際が異なるため記憶が異なる。記憶が異なることから認知モデルが独自であり、一人一人(知っていること, できること)が異なる。
我々は2つの身体を持つ認知の中で生きている。自己が個物身体を介し共同体身体で欲求を満たす。個物身体と共同体身体の関係の質が良好でないと欲求を満たすことが難しくなる。((嘘, 独り占め), (搾取, 支配))は個物身体と共同体身体との関係の質を悪化させる。欧米は植民地主義以降、根強い選民思想が障害となり、非欧米諸国との関係の質を改善できなかった。そして、BRICSの台頭により、G7諸国よりBRICS諸国の方がGDP合計が上回ってしまった。ロシアを経済制裁している国の人口は世界人口の15%。残りの85%の国はロシアを経済制裁していない。これは、長年、欧米が非欧米圏を(搾取, 支配)してきたことによる関係悪化。その手法は(嘘, 独り占め)。
債務貨幣制度は通貨発行時に必ず利子がつく。だから、返済時には受け取った通貨だけでは完済できない。最初に通貨を受け取ったヒトは、2番目に通貨を受け取るヒトが現れない限り借金を返済できない。この欠陥のある債務貨幣制度は誰かがお金を借り続けることで動く。
通貨発行陵が増えると、その通貨を発行した国の製品を輸入する国がなくなると、その国は自給自足するしかなくなる。
日本では、江戸時代まで、食糧は自給自足でした。基金があると餓死したり、村の高齢者は姥捨山に連れて行かれて村の生活から離脱しました。不食の人になれば、食糧は不要となる。
来年の日本教師教育学会に向けて、これまでの学校教育を振り返る。
学習前の私の学校に対する理解は次のとおり。
現在の学校教育は国が方針を決めている。
学校の原型は部落や村における生産の科学知識技術の伝承。すなわち、生産現場において行われた。
そして、人間関係でトラブルがあった時の対応における年長者との対話。
日常生活において食糧の確保と外敵からの防御の技術伝承。
現在の日本の学校は会社員を養成するためにある。
農業主体の社会から、工業化を進め、軍隊を強化する富国強兵の政策を学校教育に反映させた。
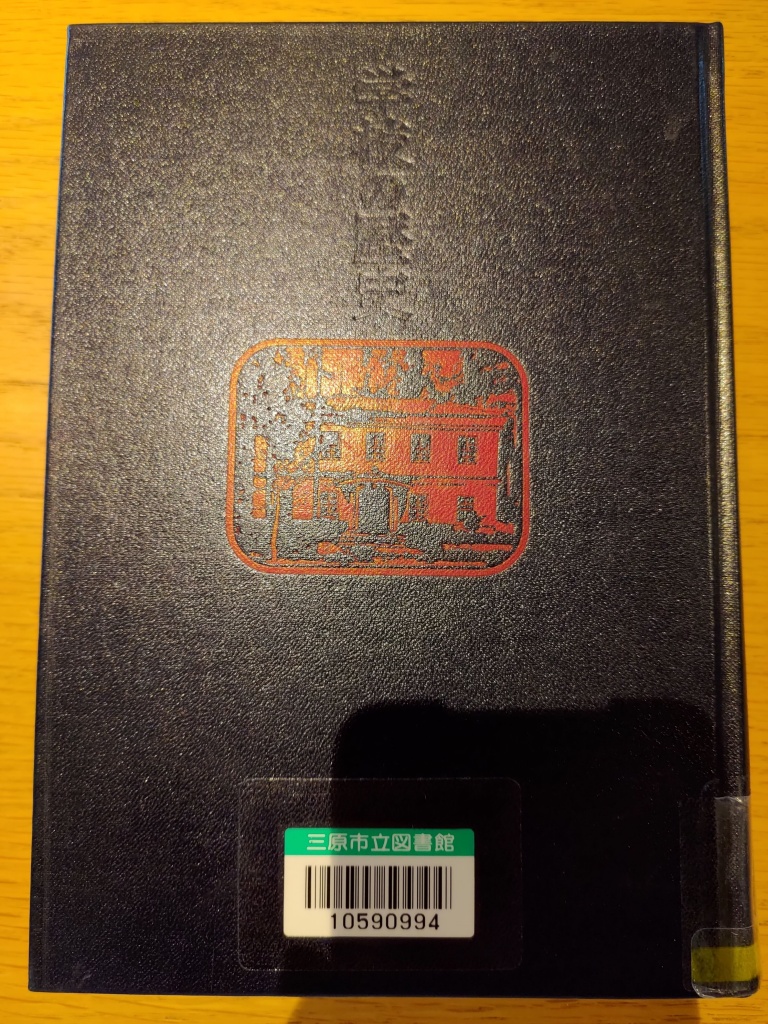
成果=Output
コメントは随時記載。
全五巻
第一巻 昭和54年(1974年)
第一巻 学校史用説明
全五巻で構成される本著作群。
本巻は全体像を示す。
以下、学習の記録。タイトルの( )はページ数
『学校の歴史』の刊行にあたって(P.1〜3)
学校は生活の中にあったが、社会的に重要な位置を占めるようになり、現代の人々は学校教育によって育成され、作り上げられている。学校は社会と切り離せない。したがって、絶えず社会の批判を受けた。そして、社会の進展に伴い改革をしてきた。学校の歴史は学校が変遷してきた歴史的背景を語る。この変遷から現代の課題を推論し、将来を展望する。
本書の特徴は次の3つ。
1 学校種別に巻別に編集
2 現在(1974年)の学校を起点に歴史を体系的にまとめた。
3 諸外国の学校の歴史を加えた。
学校教育の全体像に(政治・経済の動向, 文化史的・社会史的・生活史的な視点)を加えた
一 近代国家と公教育制度(P.3-7)
近代国家の管理運営の下に組織され発達。宗教法人や私人の管理下に置かれていた教育が国家の手に。教育は国家の重要な機能。
公教育制度の発達(P.3)
近世までの教育は社会の上層一部を対象としていたが、近代の教育はすべての国民を対象とした。この全国民を対象とした教育は近代において世界各国で認められている。我が国では明治に公教育制度が始まったので後進国。近代は国家が学校を組織し国家の管理下に置くこととして発展してきたが、近年(1974年)国民の立場から国民教育を編成しようとする動きがある。公教育は私立もカバーし、初等教育から高等教育までカバーするが、それが義務教育制度に顕著に現れている。
コメント1″国家として国民に共通目的があることを前提にした明治以降の学校教育制度。その共通目的は富国強兵、産めよ増やせよ、殖産興業。この目的は昭和バブル期に達成した。不完全な債務貨幣制度は情報の非対称性を誤用した((嘘, 独り占め),(搾取, 支配))の手段にされている。国家が国民が主体となり社会的共通資本を整備充実するために発行する通貨に金利をつける。その時、発行した通貨だけでは借金を完済できない。借金の上に借金が必要な貨幣制度。国家が全国民のために発行した通貨から金利を受け取るヒトがいる。このヒトは国家に貢献しているのか?人類史と世界の仕組みを俯瞰すると、グローバリストの下を辿って行くと、債務貨幣制度により金利でお金儲けをしている家系に帰着する。グローバリストの起点は植民地主義、植民地から宗主国への天然資源の略奪に貢献した東インド会社(英国1600年設立、オランダ1602年設立)は企業社会主義の起点となっている。グローバリズムは各国の富を8000-8500人のエリートに上納している。これからの共育にはOngoingで起きている人類の課題(人種差別=民族浄化, 貧富の差の拡大)を検知して、それを解決する能力の獲得が目的となる。”
義務教育の意義と性格(P.4)
ナショナリズムとデモクラシー。この2つの原理を支柱とし、その結合の上に教育は成立している。近代国家は国民の教育水準の向上により国力の充実と発展を進めた。この観点から義務教育制度を設けた。これがナショナリズム。一方、国民の福利増進の観点から機会均等の原則に基づくデモクラシー。近代産業の発達は初期に低賃金の単純労働者に依存したが、次第に質の高い労働力、そのため一定の水準に達した労働者が必要に。この観点から義務教育が支持された。義務教育は強制的教育と言われ国民の義務として成立したが、近年、義務ではなく国民の権利となった。このことは「日本国憲法」、下位の「教育基本法」「学校教育法」等に具体化されている。教育は国民の基本的人権の一つ。保護者に学齢児童生徒を就学する義務を負わせる、市町村に学校設置の義務、「義務教育費国庫負担法」による財務的基盤の確立。
義務教育制度の確立(P.5)
義務教育制度、諸外国の充実状況
英国 1876年(初等教育令)
仏国 1882年(法律制定)
米国 1852年(義務教育法)
日本 1872年(学制)
年限延長の実質的要因は国民の就学水準の上昇。
就学水準の上昇は(国民の生活水準, 教育に対する国民の意識の高まり)と深い関連あり。
また、近代産業の発達により教育水準の高い労働者が要求されたために就学水準が上昇。
義務教育の日本政府負担の経緯
明治後期 義務教育費国庫補助法
1918年 市町村立義務教育費国庫
1940年 義務教育費国庫負担法
義務教育は児童労働とも深い関係がある。児童労働を認めていては国民に教育を提供する義務を履行できない。
明治33年 小学校令 により学齢児童の雇用制限の規定を設け、雇用によって児童の就学を妨げない。現行制度では「労働基準法」により満15歳未満の児童を労働者にしない。
学校制度との関係(P.6)
学校教育は貴族階級と一般階級の複線だった。
義務教育は全国民の基礎的な共育システム。
教育年数が伸びることで上層階級の学校系統と大衆層の学校系統が結果的に統一された。
20世紀になると”中等教育をすべてのものに”をスローガンに中等教育の(大衆化, 義務化)が促進。
これは古いいいみの普通教育ではなく、広く職業生活への基礎教育を含む”一般教育”に変貌を遂げた。
二 学校体系の近代化(P.7-16)
単線型と複線型(P.7)
学校の構造体系には二つの類型(複線型, 単線型)がある。
現実の学校は2つの中間型をとる。
学校の起源を古代から振り返る。どんな文化でも貴族階級は文化を維持伝承する機関として学校を設立した。これは現代の指導層の学校につながる。庶民の学校は18世紀から発達を始める。19世紀中頃から近代国家の管理下に急速な発展を遂げた。これが近代初等学校の母体。
貴族の学校と大衆の学校は別々に(始まり, 発展)した。
19世紀末からは両者を統一した単一組織の学校体系が発達を始めた。
カバリー(アメリカ)は前者をヨーロッパの階級的複線型((二重組織=階級的学校組織), 複線型)、後者をアメリカの民主的単線型((梯形組織=民主的学校組織), 単線型)と呼ばれるようになった。
この中間型としてヒルカー(ドイツ)はフォーク型を加えた。フォーク型は初等教育の中途、または、中等教育の段階から分離するので複線型となる。
コメント2:階級社会:ヨーロッパでは貴族と大衆が別々の学校体系を持つところから始まった。17世紀、イタリアではイエズス会が学校(コレジオロマーノ, コレジオ)をイタリア全土に普及させた。イエズス会の学校はイエズス会の「真理」のプロパガンダ機関。一つの視点を強要する全体主義と平和と調和の新しい時代は、絶対的真理の強制によってではなく、共有の(知識, 真理)を、緩やかに、不完全ながらも体系的に蓄積することを通じてもたらされると信じる自由民主主義。学習者のための学校では階級社会をどのように扱うのか?階級社会が機能していれば、#ベンヤミンネタニヤフ さんのガザにおけるパレスチナの民のジェノサイドは止められるだろう。止められていないのは階級社会が機能していないのか?階級社会が世界中の民の幸せを実現しないことを示している。
単線化の動向(P.9)
近代学校史の動向から一般的に階級的複線型から民主的単線型の方向に発展している。
アメリカは初期には複線型であった。ヨーロッパも20世紀からは単線型に移行している、
単線型には民主化における教育の機会均等の原理がある。
複線型には貴族と大衆を分離して大衆は能力があっても中等教育さえも受ける機会がない階層的な社会に即応し、民主主義の立場では不合理な学校体系。そして、社会における対立を助長している。
この相違は単線型はナショナリズムの手段になることを示している。
現代において複線型が根強く残っている。考えられる原因を2つ挙げる。1 学校の発達の歴史が地域の社会生活、伝統と結びつき社会の教育観・学校観に強く支えられているから。2 現実の社会が十分に社会化されていなくて階層が残っているから。
学校制度の改革により社会そのものの改造が可能である。
民主的複線化(P.10)
単線型は”民主的単線型”、複線型は”階級的複線型”であるとされる。
学校制度の多様化は複線化であり、民主的でないのか?
義務教育より上の学校では常に正規の学校教育を受けていない同年齢層の国民が多数存在している。これは、学校体系の複線型よりも根本的な複線型。この両者の溝を埋めることが民主的。近代学校制度は一層多くの国民を学校教育の組織に編成する制度が好ましい。
コメント3: 筆者がここで使う民主的という意味はどういうことなのか?学校に行きたい人、行きたくない人がいる。この文脈で使っている民主的には同意し兼ねる。この文脈では資本家は好しからず階層になりそう。AIやロボットを導入して社員を解雇する企業が出てきている。AIとロボットをお金持ちがお金儲けの手段にし続けると圧倒的多数から恨まれることになる。AIとロボットは地域自給自治社会に回帰する有力な手段とする。それが人類のソフトランディングな物語。”
1899年中等諸学校の制度整備 ①中学校 ②高等女学校 ③実業学校 それ以前の複雑多様な体制を単線化の方向に進めた。
コメント4:人は一人一望みがあり(知っていること, できること)が異なる。この事実から本来、カリキュラムは生徒本人が計画することが望ましい。この時代は富国強兵を推進する時代。画一的な能力を備えた勤勉な国民の養成を企図している。”
新しい学校体系は複線的であっても民主的。社会的・経済的条件による不当な差別を排除した民主的多様化を基本とする。個人の個性や能力に応じる共育、社会的要請に基づく教育を正しく結合することを複雑化の基本原理とする。これらは相対的、抽象的概念。
就学者の増加と学校の質的変化(P.12)
日本では1899年の中等諸学校の制度整備の前後で就学率が激増している。表1より 1890年48.93%→1900年81.48%
コメント5: 1717年以前より人類支配を目的に活動している死の血盟団。支配形態は人類を悪魔崇拝にすること。その手法の一つが家族制度の崩壊。人類の伝統的な文化を破壊する。学校は子供を集団で親から隔離する手段。日本の富国強兵は武力により植民地になることを防ぐ目的があり、西洋の社会システムを導入した。近年では米国におけるLGBTQ法案が学校において保護者の知らないところで生徒に性転換を進める現実を導き出している。”
本文ではここで小学生の生徒数の激増を示している。これは単純にベビーブームであれば就学率が同じでも生徒数は増えるので割愛する。
先に引用した表1の最終年1940年は就学率99.65%になっている。
学校改革は日本のみならず、米国、欧州でも起きた。
フランスではこの期間文盲率が低下した。表2より 結婚調査における文盲率 1790年(男53.0%、女73.0%)→1901年(男4.4%、女6.3%)
表3では、プロテスタント中心の国家とカトリック中心の国家で、初等学校生徒数に対する中等学校生徒数の比率が示されている。プロテスタント国の方がカトリック国よりも比率が高い。
コメント6:カトリック国は親の職業を継ぐ人が多いということか。表1から表3まで提示されているデータと産業革命との関連について論述していない。18世紀後半から始まる産業革命はイングランドの非農業人口の比率を、1600年頃のおよそ30%から、1800年頃までには60%以上に上昇させました(20251120 GoogleGemini曰く)。動力源と生産機械の開発は事業の従事者を必要として、学校改革が行われたものと指摘する。
就学水準の上昇と学校体系
表4と表5には就学状況の変化を各学年における就学率として示している。二つの図表を合わせて1875年から1910年まで徐々に最高学年まで就学する生徒の比率は増えた。
義務教育制度を支える実質的な基盤は国民の就学水準。
三 教育の近代化と伝統(P.16-20)
教育的伝統の継承
近代教育史の考察には教育的伝統の解明が重要。ハンズの「比較教育(1949)」。
本書での分類
(1)自然的要素
①人種的要素
②言語的要素
③地理的及び経済的要素
(2)宗教的要素
①ヨーロッパの宗教的伝統
②カトリックの伝統
③英国国教の伝統
④清教の伝統
(3)非生協適用
①人文主義
②社会主義
③国家主義
各国の教育は独自の民族的、歴史的、文化的な伝統を直継承している。その上で、先進国の教育を比較している。
文明開化の教育と復古的政策(P.17)
我が国の近代の教育は、欧米の先進国の教育と模範として成立。急速に近代化。同時に近世までの伝統的な教育思想及び教育内容が継承された。この経緯は欧米とは異なる我が国独自の歩みであった。我が国の教育の近代化は、江戸時代後期以降発達した「洋学」が起点となった。明治維新後は文明開化によって。教育の近代化が急速に進んだ要因の一つには幕末における伝統的な文化と教育の高い水準がある。
1872年の学生発布。近世以来の儒学と漢籍や往来物などが広く使用され、小学校の学習内容は、習字や算盤が主要。
1877年の西南の役の頃を境に復古的傾向が時代の表面に現れるように。元田永孚の「教学聖旨」を契機に文明開花に批判が高まる。そして、仁義忠孝を基本とする東洋道徳の復興、国風の尊重が唱えられるに至る。
文部省はこの頃から儒教呪義的皇国を基本とする方針に転換。
思想としては復古したが近代化は推進された。ペスタロッチの「開発主義教授法」、メイソンの西洋音楽、リーランドの洋式体操が学校教育に取り入れられた。
国家体制と教育政策(P.18)
1885年の内閣制度、その後大日本帝国憲法。初代文相森有礼さんは、国家主義教育政策を実施、その後、教育は強い国家体制のもとに。1890年に教育勅語が発布。国民の道徳と教育の根本理念が示された;内容は伝統を継承し、形態は近代化した。
大正期の新教育運動は、大正デモクラシーの社会思想を背景とした自由主義・児童中心主義の教育。この運動は上層階級の子供を対象とする私立学校や師範学校附属小学校を中心に展開。全国の公立学校には普及せず。
1933年以降採用された色刷りの教科書から。満州事変後であったため、国家主義的な教材や戦時教材が多く取り入れられている。
戦時下の教育と戦後の改革(P.19)
日華事変、太平洋戦争。教育が戦時体制の一環として編成。同時に学校制度を近代化。「中等学校令」の制定により中等諸学校の統一、師範学校の専門学校程度への昇格。
第二次世界大戦後、民主主義による教育の機会均等、六三三四制、の戦後の新教育。
大正期の新教育運動の復興、より社会性の強い一面があった。
占領下の与えられた民主主義と同様、与えられた新教育であった。従って、伝統的な社会意識や教育観に阻まれて円滑な実施が妨げられた。我が国の教育の近代化は伝統の継承との間に相剋と融合を繰り返した。
コメント7:教育の伝統と近代化の相剋にはどんなことがあったのだろう?
産業の発達と近代学校(P.20-P.24)
近代社会の性格は、産業革命による近代産業の発達によって根本的に規定される。近代産業及び産業教育の発達によって学校観が変革。
産業教育の発達(P.20)
おわりに=Outcome
関連記事
-

-
45年前に決めたゴール
Check学習の記録 学校の歴史「ここで明らかなのは不明領域を明らかにする『技術 …
-

-
折り合いをつけて習慣を変える
Check学習の記録 学校の歴史あなたの意思決定が世界を創る。 意思決定コンサル …
-

-
あなたのストーリーに登場するAI
Check学習の記録 学校の歴史「AI(人工知能)が話題にならない日はありません …
-

-
課題設定能力
Check学習の記録 学校の歴史「このアルゴリズムは、人間関係を含む様々な環境の …
-

-
認知の壁を突破する
Check学習の記録 学校の歴史「0から何かを生み出し、その生み出されたモノから …
-

-
愛ある言葉の役割
Check学習の記録 学校の歴史一昨日と昨日、今、受講しているコーチング・コース …
-

-
理解することと同意することは違う
Check学習の記録 学校の歴史「新薬開発は不明領域を相手にしています(第0章参 …
-

-
メンタリティの実践 勝ちたい気持ちが強い方が勝つ
Check学習の記録 学校の歴史「振り返ると、この子供の頃の夢中になる体験が今の …
-

-
地域活性化志向の原点
Check学習の記録 学校の歴史2021年4月6日執筆開始 4月7日脱稿 あなた …
-

-
個人と組織 境界のある和と和を和する
Check学習の記録 学校の歴史「『自分を愛し、相手を愛する』。自分を愛せないと …