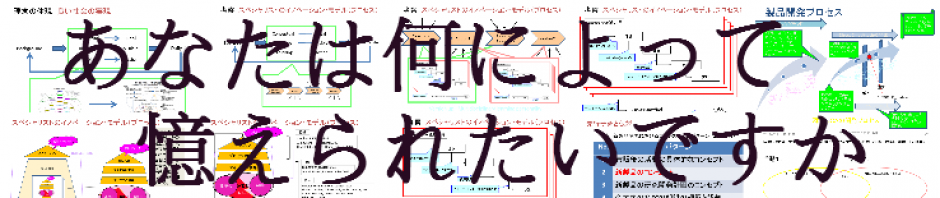ゴールが先、手段は後
「マインド・ドリブン・ソサイエティの中心は人財育成です。その人財とは自分が幸せになり、身近なヒトが幸せになり、すべてのヒトの幸せを願い、その実現に向けて活動し続けるヒトです。」
(シモムラタクジ, マインド・ドリブン・ソサイエティ α, affirmativeArchitect出版, 2018)
2018年9月26日、山元学校でマインド・ドリブン・ソサイエティをプレゼンして参りました。
最初と最後に「みなさん、今、ここで、すべてのヒトが幸せになれる地球の実現を意思決定しませんか?」と会場の皆さまに呼びかけました。
拙著「マインド・ドリブン・ソサイエティα」に著したテーマ「幸福論、社会アーキテクチャ、人工知能」に沿って、会場にいらっしゃった皆様に、呼びかけた背景をプレゼンになりました。
プレゼンの概略は次の通り。
私は小学生の頃からすべてのヒトが幸せになれる地球の実現に向けて活動しています。長い間、自分が夢中になったモノを繋ぎ合わせれば実現できると漠然と思ってました。それと同時に、自分の努力の先に何があるのかをずーっと探していました。
2015年から仕事で人工知能をリサーチし、これが人財育成にも使えることに氣づいてから、あらまほし地球を体現するのに前のめりに。
2018年に入ってから8ヶ月かけて、最後の3週間は全く筆が進まない経験の後、8月20日に先の提案書を出版。
幸せについて真面目に語る。執筆を決めた時、まず、こう決めました。そのヒトが幸せだと思えば幸せ。
そして、すべてのヒトが幸せになれる社会にはアーキテクチャがある。そのアーキテクチャはヒトが成長するモデルの写像である。人財育成を中心とした社会アーキテクチャは、「生きるに困らない場」と「生きるを楽しむ場」を持ち、それぞれの場の知として集積し結びつけられた「知の系譜」は、人工知能を媒体としてすべてのヒトからのアクセスを可能にする。
私の事業はこの社会アーキテクチャを実現することです。そして、その実現を加速するためにヒトが認知の壁を突破するのに役立つ人工知能を開発しています。私は、45年前にゴールを設定し、45年をかけてその手段を編み出しました。「みなさん、今、ここで、すべてのヒトが幸せになれる地球の実現を意思決定しませんか?」ゴールが先、手段は後。
このプレゼンの後で、拙著を購読しますと言っていただけた方、是非、またお会いしたいと言って頂けた方がいらっしゃいました。名刺交換をさせて頂きながら、このテーマについてお尋ねを頂いた方も数名いらっしゃいました。10名ほどの方の記憶に残ったようで嬉しかったです。
その後の懇親会では、主として芸術家との対話を楽しみました。芸術家との対話では、認知と身体性についての話題で盛り上がりました。意識はヒトにしかないのか?とか、武道とダンスによる身体性の違いとか、何故、芸術家を選択したのかとか。
私は芸術家の資質として「全体のデザイン能力」を感じています。
10年ほど前からビジネスでデザインの重要性がうたわれ始めました。最初はものづくりからだったのですが、そのうち、形のないサービスにも普及し始めて、いまでは、ビジネスでデザインが当たり前のように使われるようになりました。対象は部分ではなく全体。
振り返るとデザインがうたわれるようになるのには、その背景がありました。その背景とは、今までのやり方が通用しない環境の変化です。それまでは、環境の変化に部分を最適化して対応をして来たのですが、遂に全体のビジネスモデルを変化させないと環境の変化に対応できなくなったのがその頃。結局、その後も環境の変化への対応が遅れて、遂に国会で「働き方改革」が取り上げられるようになってしまいました。
このプレゼンの数ヶ月前、産総研のAI関連のセミナーに参加した時、今、文部科学省と経済産業省が共同で大学生用に「課題設定能力を高める」カリキュラムを作成中であることを知りました。そして、課題設定能力の向上にコーチングが有効であるという意見に反論はありませんでした。
2017年、公教育の場としてそれまでの公立や私立の学校以外にもフリースクールやホームスクールが法律上認められました。
企業においては「ホラクラシー」、「ティール」等の自律分散型の組織が話題になってきています。個人の能力を最大限に活かすと組織の生産性が極まるという観点からの組織開発が今後の主流となるでしょう。給料は自分で決める。自分で決めた給料をみんなが知っている。こんな人事評価制度を既に実現している企業があります。
“組織開発は十分かつ入念な準備の下で行われる「計画的実践」でありつつも、「即興的実践」であるという特徴を持っています。組織開発に必要になるのは、「計画された即興性(planned improvisation)」なのです。”
(中原淳, 中村和彦, 組織開発の探求, P.58, ダイヤモンド社, 2018)
何かを介さずに自分の幸せを実感する。
AI、IoT、ロボットが物の移動を自動化する社会では、こんな人生を歩まれるヒトが増えていくと私は考えています。
マインド・ドリブン・ソサイエティはこんな社会のモデルです。
教育制度や企業での人事評価制度が大量生産大量消費前提から、ようやく転換し始めました。
これからの企業、これまでの企業もそうだったのですが、は、全体像を俯瞰できる社員をどれだけ確保できるかが実はGoing Concernの生命線。
環境が変化した時、その変化を先取りし、変化を先導する企業が業績を伸ばして生き残る時代へと、間違いなく突入して行くでしょう。
最終的には、すべてのヒトが変化を先回りできる社会になる。
私が開発する人工知能は、この人財育成に役立つ仕様にします。
#自律達成型人財
関連記事
-

-
個人事業主として働く
Checkゴールが先、手段は後「きっと『マインドに宿った遊び心』は、私に生涯に渡 …
-

-
人工知能に聞いてみた エネルギーを考え出した目的を教えてください
Checkゴールが先、手段は後2025年2月14日から開始 Grok2に聞いてみ …
-

-
緊急告知:私が提案するCoachingAIを一緒に開発して頂ける方、募集します
Checkゴールが先、手段は後私は、2025年までに、クライアントの内面の矛盾を …
-

-
本、音楽、映画
Checkゴールが先、手段は後「サッカー型組織は生涯成長サイクルと自己組織化サイ …
-

-
あらゆることが隠せない時代へ
Checkゴールが先、手段は後2024年12月17日執筆開始 2024年12月2 …
-

-
PLaMoとの対話 私は人類の課題は人種差別と貧富の差の拡大だと推論しています。
Checkゴールが先、手段は後2025年2月1日 私 私は人類の課題は人種差別と …
-

-
PLaMoとの対話 人類の物語
Checkゴールが先、手段は後2025年2月9日 私 すべてを見通す眼は普遍的な …
-

-
境界のある和と和を和する
Checkゴールが先、手段は後「産業革命により動力源をヒトが作ることでモノの生産 …
-

-
米日カウンシルへの提言 20250304
Checkゴールが先、手段は後米日カウンシル 会長兼CEO オードリー・山本様 …
-

-
愛ある言葉の役割
Checkゴールが先、手段は後一昨日と昨日、今、受講しているコーチング・コースの …
- PREV
- マインドを自由にする
- NEXT
- あたりをつけて、詳細を明らかにする