意思決定 by T. S.
2019/01/21
皆さんお早うございます。理念を磨け、新たな価値の連鎖を生み出せ、意思決定スタイリストの SHIMOMURA Takuji です。
「即断即決が意思決定の究極のスタイルです。磨き方次第で、誰もが獲得することが可能です。」
プロローグ
私が成長のポイントにしていたことに意思決定があります。
意思決定の前には目的があり、後には行動があります。
あなたの臨場感は意思決定を構成する要素のひとつです。
意思決定のスタイルを磨くことにより目的に直結した行動がとれるようになります。
目的に直結した行動特性は、理念の体現を加速します。
即断即決。
これが意思決定の究極のスタイルです。
どうしたら、即断即決できるようになるのでしょうか。
今回は、このテーマについて考えてみました。
意思決定は常
私は身近な意思決定として会話を位置付けています。
会話は意思決定の連続です。
会話の起点と終点を振り返って見ましょう。
GAPの発生
会話の起点は自分が話しかけること、若しくは相手から話しかけられることですね。
相手に何らかの興味を持って、必要性があって、あなたは相手に話しかけます。
あなたに何らかの興味を持って、必要性があって、相手はあなたに話しかけます。
あなたの中に発生したGAP(無から有)が、若しくは相手の中に発生したGAP(無から有)が会話の起点になります。
その目的が目の前の人と楽しむことであれば、楽しくて表情が和み、笑い声が出るような話題になります。
目的地までの道筋を理解することであれば、道筋を理解する話題になります。
発生したトラブルを解消することであれば、トラブルの原因を特定し、原因を排除するための方策を特定し、原因を排除するまでの話題になります。
新しい仕事を始めることであれば、今の会社のヴィジョンや活用可能な資源から新しい仕事を特定し、その仕事のビジネスモデルを設計し、それを始めるまでの手順を設定し、その手順を修正しながら新しい仕事を開始、その後、定着するまでの話題になります。
更に、会話の話題を変更することがあります。
会話の目的を達成しないまま話題を変更するのは、別の話題で目的を達成するためです。それまでの話題では目的を達成できない、若しくは達成するまでに長時間必要になると判断した結果、私は話題を変更しています。
あなたの中に発生したGAP(このままでは目的が達成できない)が、若しくは相手の中に発生したGAP(このままでは目的が達成できない)が話題を変更する起点になります。
Backgroundの形成
意思決定(目的が達成できたとする意思決定を含む)の瞬間までBackgroundの形成が続きます。
(Backgroundisation参照、ゴールを意思決定に読み替えて下さい)。
Backgroundisationはある会話が始まる前からあなたも、相手も行っていることです。
意思決定におけるBackgroundは判断基準になります。
例えば、「会話を楽しむことができた」とする判断基準は、「相手が笑顔になり、笑い声が出る」になります。私は、ここ数年間、初対面の方とサッカーの話題で盛り上がっています。
「目的地までの道筋を理解できた」とする判断基準は、「移動手段と通過点を特定できる」になります。現在地から徒歩でA駅まで行って、B駅まで電車で移動して、そこから徒歩でCビルディングに移動する。
「生産において発生したトラブルを解消した」とする判断基準は、「安定稼働」になります。最終製品Aの収率が規格を切ってしまった。原因を調査したところ中間製品Bの生産において、生産設備Cの部品Dの取り付け幅に問題があった。取り付け幅をE㎜ではなく、F㎜にする(トラブルの原因は部品Dの取り付け幅)。
「新しい仕事を開始できた」とする判断基準は、「新しい仕事が会社の経営に組み込まれた」になります。「すべては社会を良くして行くために」という理念を体現するために、プログラムAを販売する。これは、B能力を高めた顧客が自身の仕事を通じて社会への貢献度を高めて行くことをヴィジョンとする。自身のB能力を高めることに意識の高い中小企業の社長を対象にフロントエンドセミナーを実施する。毎回、C%以上のバックエンド商品へのコンバージョン率を獲得により、ここ2年間は年間D円以上の売り上げを獲得できている。
このように会話を通じて、様々な場面における意思決定のBackgroundを形成します。
GAPの克服
発生したGAPがあなたの内面にあれば、内面にGAPが無くなることが意思決定の終点になります。
発生したGAPがあなたの外面にあれば、外面にGAPが無くなることが意思決定の終点になります。
発生したGAPは意思決定の繰り返しで克服するモノです。
意思決定の度にBackgroundは書き換えられます。
Backgroundを書き換えた経過が、GAPを克服した経過となります。
この経過は次のGAPを克服する際のBackgroundになります。
大きな意思決定は小さな意思決定の積み重ねです。小さな意思決定にも起点と終点があります。
意思決定の実際は、目的を達成するまでに様々な意思決定をしています。
例えば、「初対面の方と、サッカーの話題で盛り上がる」場合。私が2022年までに(男子)日本がワールドカップで優勝するために2003年から活動していることを伝える(楽しむ-意思決定1)。その過程で出会った人達との会話を伝える(楽しむ-意思決定2)。優勝するまでのシナリオを伝える(楽しむ-意思決定3)。次のワールドカップに向けての具体的な活動を伝える(楽しむ-意思決定4)。私の顔が自然と笑顔になっており、相手の反応から笑い声になることもある。それにつられて、相手も笑顔になり、笑い声が出た。会話を楽しめた(楽しむ-意思決定5)。
「目的地までの道筋を理解できた」の場合。Cビルディングまで約束の時間の5分前までに徒歩では行けない。別の交通手段で行く(道筋-意思決定1)。約束の時間に間に合う交通手段は、電車かバスかタクシー。タクシーの利用は上司の許可が必要なので使わない(道筋-意思決定2)。バスでも間に合うが、渋滞で遅れるリスクが有る。バスと電車の運賃差は50円。遅刻のリスクをコントロールするために電車を選択(道筋-意思決定3)。現在地から最寄の駅はD駅だが、B駅まで乗換が2回若しくは、乗換1回でE駅からCビルディングまで歩くことも可能だが遅刻のリスクがある(道筋-意思決定4)。5分前までにCビルディングに到着することを考えると、少し遠いが、乗換なしでB駅まで行けるA駅から電車に乗ることにする(道筋-意思決定5)。道筋が理解できた(道筋-意思決定6)。
次に、トラブル発生後の「安定稼働」の場合。中間製品Bが他の3つの中間製品に比べて収率が低い。その事象は、軸間距離が低値側で規格外になっている中間製品Bの多いことを特定(生産-意思決定1)。次に、軸を取り付ける生産設備Cの状態を点検することにした(生産-意思決定2)。その結果、生産設備Cで製品Aの軸を形成する部品Dの取付け幅が規格内にあるがEmmと低値側に寄っていることを特定(生産-意思決定3)。取り付け幅をGmmとして試運転することを決めた(生産-意思決定4)。試運転の結果、収率はもっと上げることが出来るので取り付け幅を更に変更すると決めた(生産-意思決定5)。試行錯誤の結果、取り付け幅をFmmにした(生産-意思決定6)。安定稼働を実現した(生産-意思決定7)。
最後に、「新しい仕事が会社の経営に組み込まれた」場合。新しい仕事も経営理念に従うことを決定(仕事-意思決定1)。新しい仕事は製品ではなく顧客の能力開発プログラムに決定(仕事-意思決定2)。高めるのは顧客のB能力に決定(仕事-意思決定3)。ターゲットは30~40代のサラリーマン、中小企業の社長のどちらにするか議論が続いたが、B能力を高めることに意識の高い中小企業の社長に決定(仕事-意思決定4)。5つのプログラムの中からプログラムAに決定(仕事-意思決定5)。プロモーションは本の出版、業者への委託、セミナーによる販売の中からセミナーによる販売に決定(仕事-意思決定6)。当初、予定していたコンバージョン率はC%を上回り、ここ2年間で年間D円以上の売り上げを獲得できたため、経営に組み込まれたと判断した(仕事-意思決定7)。
これは会話を通じて形成された「意思決定のフラクタル*1」と言えます。
ひとつの意思決定は、そこに至るまでに細分化された意思決定のプロセスを経て行われます。つまり行動の前には、そこに至るまでの一連の意思決定があります。
意思決定のフラクタル
「意思決定のフラクタル」の本質は「あなた自身の内面と外面を統合するプログラム、アルゴリズム」です。
あなたがコンフォートゾーンの外にゴールを設定するのも、ゴールに臨場感を持つのも、アファメーションによりゴールを達成するのも、あなたの「意思決定のフラクタル」を介して行っています。
また、小さく始めたモノが大きく育つのも、複雑な現象をシンプルに理解できるのも、「意思決定のフラクタル」をあなたが持っているからです。
意思決定はGAPの発生に始まり、Backgroundの形成を経て、GAPを克服することで終了します。
今回、会話を例にとって、その経過を考えました。
会話は「即断即決」の繰り返しです。
あなたも、相手も、会話を始める前からBackgroundの形成を始めています。
「向こうの向こうのBackground」(お互いが出会う前のBackground)から、「向こうのBackground」(お互いが出会ってからのBackground)を形成し、そこから「手前のBackground」(直後に意思表明するためのBackground)を形成します。意思表明の度に「手前のBackground」が書き換えられ、「向こうのBackground」が書き換えられます。ひとつの話題を終えると「向こうの向こうのBackground」が書き換えられます。
(この詳細は Backgroundisation 参照)
3つの階層のBackgroundには、目的に応じた「意思決定のフラクタル」が形成されます。
「意思決定のフラクタル」は起点から終点に至るフローチャートの全体像です。その実際は、最小単位の意思決定のプログラム、アルゴリズムを状況に適用することの繰り返しです。
「意思決定のフラクタル」には2種類あります。自らの意志により目的を達成するためのプログラム、アルゴリズムを意識に書き込んだ直後に、それに従い意思決定を繰り返す「柔らかい意思決定のフラクタル」(1)と、仮決めしたプログラム、アルゴリズムに従い意思決定を繰り返す「固い意思決定のフラクタル」(2)に分かれます。(2)が即断即決の前提になります。
どちらも、あなたの判断基準と判断根拠との瞬間的な照合を繰り返しています。
「固い意思決定のフラクタル」は目的とする意思決定を行うための判断基準が全て揃っている状態です。
「柔らかい意思決定のフラクタル」は目的とする意思決定を行うための判断基準がほとんど揃っていない状態です。
「柔らかい意思決定のフラクタル」から「固い意思決定のフラクタル」に変化する過程を考えてみましょう。
「柔らかい意思決定のフラクタル」とは仮決めの判断基準で意思決定をしている状態です。従って、次の段階に向けて行動しながらも前工程に戻ります。「行ったり、来たり」を繰り返す、モヤモヤとした状態です。
「固い意思決定のフラクタル」とは判断基準が全て揃ったと判断し、その判断基準に従い、意思決定と行動を繰り返している状態です。この場合も仮決めの判断基準に従って意思決定と行動を繰り返しています。目的を達成するまで意思決定と行動(予測とプレー)の精度を上げて行きます。
あなたの「柔らかい意思決定のフラクタル」は、あなたの行動の何故(why)、何を選択するのか(what)、どうやるのか(how)を問い続け、判断基準(Success Measure)の Scrap and Build を繰り返すことで「固い意思決定のフラクタル」へと変化して行きます。
即断即決が意思決定の究極のスタイルです。磨き方次第で、誰もが獲得できます。
エピローグ
その目的を選んだのは何故か?(why)
それを達成するために何を選択するのか?(what)
どうやるのか?(how)
その目的の達成したことは何を持って判断するのか?(Success Measure)
「柔らかい意思決定のフラクタル」を「固い意思決定のフラクタル」にするための鍵は、この4つの問いに答えるプロセスとその答えにあります。
あなたの Success Measure は何ですか?
*1 フラクタル 図形の部分と全体が自己相似になっているものなどをいう。血管の分岐構造や腸の内壁などはフラクタル構造であるが、それは次のような理由によるものだろうと考えられている。例えば血管の配置を考えたとき、生物において体積は有限であり貴重なリソースであると言えるので、血管が占有する体積は可能な限り小さいことが望ましい。一方、ガス交換等に使える血管表面積は可能な限り大きく取れるほうが良い。このような目的からすると、有限の体積の中に無限の表面積を包含できるフラクタル構造は非常に合理的かつ効率的であることが解る。しかも、このような構造を生成するために必要な設計情報も、比較的単純な手続きの再帰的な適用で済まされるので、遺伝情報に占める割合もごく少量で済むものと考えられる。 20140418 wikipedia フラクタル より抜粋して引用
関連記事
-

-
man model Marketing
Check意思決定 by T. S. 事業内容 コーチングと組織開発を用いた人財 …
-

-
創造的かつ実行可能な戦略代替案-戦略代替案創造のための基本コンセプト by 籠屋邦夫さん
Check意思決定 by T. S.理念を磨け、新たな価値の連鎖を生み出せ。あな …
-

-
個人と組織 境界のある和と和を和する
Check意思決定 by T. S.「『自分を愛し、相手を愛する』。自分を愛せな …
-

-
【質問】エロヒムとヤハウェ(下村)
Check意思決定 by T. S.立教大学 文学部 キリスト教学科 教授 長谷 …
-

-
【告知】 みちみち 生活充実講座 働き世代コース(2024年9月)
Check意思決定 by T. S.2024年7月4日 三原市民の皆様 「生活充 …
-

-
人財育成を中心とした街つくりの設計図 学校と図書館の役割
Check意思決定 by T. S.「ヒトの本質は可能性だと考えています。本人が …
-

-
資料 ete Japan株式会社
Check意思決定 by T. S.2025年4月1日より 20250401 ひ …
-

-
Report 私が理解している #人類史と世界の仕組み(下村)
Check意思決定 by T. S.2024年5月23日 0 はじめに(Back …
-

-
革新的人財育成プログラム
Check意思決定 by T. S.あなたをイノベーション体質にします。 イノベ …
-

-
ビッグバン共育説明会
Check意思決定 by T. S.2021年4月12日執筆 ビッグバン共育 社 …

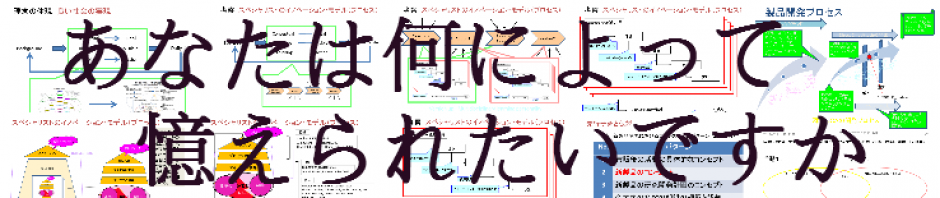


Comment
[…] 意思決定にはBackgroundがあります。更に、抽象化と具体化が我々の思考と行動の質に大きな影響を及ぼします。 […]
[…] フレームにはBackgroundがあります。そのBackgroundを最適化して、ゴール到達の観点から「目的」「切り口」「範囲」として適切であることをコンセプト・レビューしましょう。そのレビュ […]